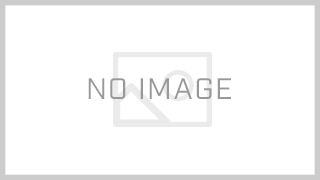今までの記事のおさらいを交えて、新NISAを活用する上で失敗しないためのコツを紹介します。
NISA制度を理解する
2024年から開始した新NISA制度は、非課税期間が恒久化されました。投資枠や運用ルールを把握しておくことが重要です。特に「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の違いを理解し、資産形成の目的に合わせて使い分けましょう。
▼詳しくはこちらの記事をご参照ください
長期・分散・積立
NISAは長期投資向けの制度なので、短期の値動きに惑わされず、「長期・分散・積立」を基本に運用すると安定した成果を得やすくなります。
・長期:15~20年以上の運用を想定
・分散:全世界株式や米国株式のインデックスファンドを活用
・積立:毎月一定額を投資し、ドルコスト平均法でリスクを軽減
▼詳しくはこちらの記事をご参照ください
低コストのファンドを選ぶ
投資信託には信託報酬(運用コスト)がかかります。
例えば、eMAXIS Slimシリーズのような低コストのインデックスファンドを選ぶと、長期的な利益を最大化しやすくなります。
▼詳しくはこちらをご参照ください
インデックスファンドの手数料の重要性!長期投資への影響をシミュレーション!
下落時に慌てない
NISAは非課税メリットを最大限活かすために長期投資が基本です。短期売買を繰り返すと、せっかくの非課税メリットを十分に活用できないため、短期売買を避けることが大切です。また、投資を続けていると、一時的な株価の下落は避けられません。しかし、過去のデータでは長期的には株価が成長していることが分かっています。そのため、株価の下落に一喜一憂しないためにも生活資金を圧迫しない範囲で投資をすることをおすすめします。また、急な出費にも対応できるよう、生活防衛資金を確保してから投資を始めましょう。
定期的な見直し
投資方針を決めたら基本的には放置でいいのですが、年に1回程度は運用状況をチェックしましょう。
特に以下の点を確認するとよいです。
・ポートフォリオのバランス(分散投資ができているか)
・手数料が安い新しいファンドが登場していないか
・目標に合った運用ができているか
まとめ
・NISAの制度を理解する(つみたて投資枠と成長投資枠の使い分け)
・長期・分散・積立を意識する(コツコツ積み立てる)
・低コストの商品を選ぶ(信託報酬をチェック)
・相場が下落しても慌てない(非課税メリットを活かす・長期視点で投資を続ける・生活防衛資金の確保)
・定期的に運用状況を見直す(目標に合っているか確認)
この5つを意識すれば、NISAで失敗するリスクを大幅に減らせます!