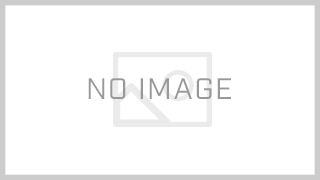2月下旬からの株価下落は記憶に新しいと思います。ここ数日で回復傾向にはあるものの、関税問題や地政学リスクなど、まだまだ不透明な要因も多く相場が読みにくい状態が続いています。
こうした相場環境の中で重要になるのが「リスク許容度」です。投資では「リスクを取らなければリターンも得られない」と言われていますが、どれくらいのリスクを取るべきかは人によって異なります。特にNISAでは、売却をすると翌年まで枠が復活しないため、自分に合ったリスク許容度を把握することが重要です。
この記事では、リスク許容度の考え方と、自分に合った投資戦略を見つけるためのQ&Aを紹介します。
今回の記事はこんな人にオススメ
・NISAを始めたけど、どれくらいリスクを取るべきか分からない
・暴落時に不安にならずに運用したい
・自分に合った投資戦略を見つけたい
リスク許容度とは
「リスク許容度」とは、投資で損失が出ても精神的・経済的に耐えられる範囲のことです。
具体的には、以下のような点を考慮します。
・価格変動に耐えられるか?(一時的な下落で不安にならないか)
・投資資金が生活に影響を与えないか?(余剰資金で運用できているか)
・長期的な視点を持てるか?(短期間の利益を求めすぎていないか)
NISAでは長期運用が前提のため、自分のリスク許容度に合った資産配分をすることが大切です。
リスク許容度を決める要素
リスク許容度を決める3つの要素
1.年齢・ライフステージ
・若いほどリスク許容度が高い(時間があるため回復できる)
・50代以降は守りの資産運用を考える
例
・20代〜30代 → 株式中心のポートフォリオ(S&P500や全世界株式)
・40代〜50代 → 株式+債券のバランス型へシフト
・60代以降 → 債券比率を増やし、リスクを抑える
2.資産・収入状況
・収入が安定している人はリスクを取りやすい
・投資額が少ないうちはリスクを取ってもOK(数万円の変動は影響が少ない)
・生活費を圧迫する投資はNG(無理な積立額になっていないか確認)
例
・安定収入がある → リスク高めでもOK
・安定収入がない → 流動性を確保しつつ投資 → 現金比率を高めに
3.投資経験・メンタル
・暴落時に慌てる人または狼狽売りする人はリスク許容度が低め
・「時間分散・長期投資」の考え方が持てる人はリスク許容度が高い
・短期的な値動きに一喜一憂しないことが大切
例
・初心者 → 積立NISA中心に分散投資(S&P500や全世界株式)
・経験者 → 個別株やETFなどリスクを取る選択肢もあり
リスク許容度のセルフチェック
リスク許容度の確認方法(簡単セルフチェック)
以下の質問に「はい」or「いいえ」で答えてみましょう。
Q1. 株価が30%下がっても売らずに耐えられるか?
Q2. 生活防衛資金は確保しているか?
Q3. 投資期間は10年以上を想定しているか?
Q4. 定期的に収入があり、投資額に影響を受けにくいか?
Q5. 短期的な利益より、長期的な資産成長を重視するか?
「はい」が多いほど、リスク許容度は高い!
事項ではそれぞれについて詳しく解説します。
解説|リスク許容度セルフチェック
Q1. 株価が30%下がっても売らずに耐えられる?
・YES → リスク許容度は高め → 株式中心の運用が向いている
・NO → リスク許容度は低め → 貯金比率を高めて、債券なども加えるのが安心
解説
株式市場では、一時的に30%程度の下落は珍しくありません。例えば、S&P500指数も過去に何度も大幅な下落を経験しながら、長期的に成長を続けています。短期の値動きに惑わされず、長期視点で運用できるかがカギです。
Q2. 生活防衛資金は確保している?
・YES → リスクを取りやすい → 株式比率を高める選択肢もあり
・NO → リスクを抑えるべき → まずは現金を確保し、その後投資を始める
解説
投資は「余剰資金」で行うのが原則です。急な出費が発生しても慌てないために、生活費の3〜6ヶ月分を現金で確保しておくのが理想的です。これがない状態で投資すると、暴落時に資金が必要になり、損失が確定するリスクがあります。
Q3•Q5. 投資期間は長期を想定している?
・YES → 株式の比率を高めてもOK
・NO → リスクを抑えた運用が必要(短期間での運用は価格変動の影響を受けやすい)
解説
長期投資は、時間を味方につけることでリスクを抑えられるのが特徴です。例えば、S&P500指数の20年間のリターンはプラスになる確率がほぼ100%ですが、1年単位ではマイナスになることもあります。
NISAの非課税メリットを最大限活かすには、長期運用できる資産を選ぶことが重要です。
Q4. 定期的な収入があり、投資額に影響を受けにくい?
・YES → リスク許容度は高め → 積極的な投資も可能
・NO → リスクを抑えるべき(収入が不安定なら、現金比率を高めに)
解説
安定した収入がある人ほど、長期的に積み立てを継続しやすいです。例えば、公務員や大企業勤務の人は、安定収入があるため株式比率を高めても耐えられる可能性が高いです。
一方、収入の変動が大きい人は、現金比率を高めるのも選択肢になります。
自分に合った投資戦略
Q&Aの結果に応じて、NISAでの投資戦略を決めましょう。
具体例
| リスク許容度 | 運用の特徴 | 具体的な投資戦略 |
| 高い | 株価の変動に耐えられる | 株式中心に運用(S&P500やオルカン) |
| 中等度 | ある程度の変動は許容できる | 株式+債券など、バランス運用 |
| 低い | 大きな変動は不安 | 貯金や債券比率を高め、安定運用 |
例えば、「YES」が多かった人はS&P500や全世界株式など株式中心の運用が向いています。
一方で、「NO」が多かった人は株式の割合を抑え、貯金や債券比率を高めてバランス型の投資を心掛けると安心です。
まとめ
自分のリスク許容度を知り、無理なく運用しよう
・リスク許容度は、年齢・資産・収入・メンタルによって異なる
・Q&Aを活用して、自分に合った投資戦略を決める
・NISAは余剰資金で運用。また、長期投資を前提に、無理のない範囲でリスクを取る
【関連記事】
相場急変でS&P500下落&円高で評価額が目減り…今こそ冷静な投資判断を!
インフレで貯金は目減り、でも投資は含み損?長期投資で必要な“握力”とは?