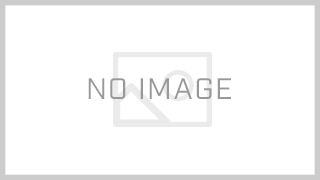「新NISAを始めたいけれど、専門用語が多くてよくわからない…」
そんな方のために最低限知っておくべき専門用語をまとめました!初心者でも理解しやすいようにわかりやすく解説していきます。
NISAの基本用語
新NISAを理解するうえで最初に知っておきたい用語
1. 新NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)
・新NISAの制度概要
・つみたて投資枠と成長投資枠の違い
⒉ 非課税期間
・「投資の利益が非課税」という意味
・旧NISAと新NISAの非課税期間の違い
⒊ 投資上限額
・年間の投資可能額(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)
・生涯投資枠1,800万円の活用方法
【さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください】
インデックスファンドに関する用語
NISAでは最初にインデックスファンドへ投資を行う方が多いため、インデックスファンドとそれに関連する用語について解説します。
⒈ インデックスファンド
インデックスファンドとは、市場全体の動きを表す代表的な指数に連動した成果を目指す投資信託のことで、パッシブファンドとも呼ばれます。
インデックス=指標
ファンド=投資信託
インデックスファンドのメリット
・値動きがわかりやすい
日経平均やTOPIX、S&P500といった指数に連動するように運用されるため、値動きがわかりやすいのが特徴です。
・幅広い銘柄や地域に分散投資が可能
特定の指数への連動を目指すため、幅広い銘柄に分散して購入します。そのため、インデックスファンドを1本購入するだけで、広範な分散投資が可能となります。また、全世界株式(オルカン)といった広範な地域への分散投資が可能なインデックスファンドも存在するため、アメリカや日本といった特定の地域へ投資するのが不安な方へおすすめの銘柄も多数存在します。
・運用コスト(信託報酬:下記で説明)が低い
信託報酬や手数料などが比較的低価格で設定されていることも魅力の一つです。数%の運用コストの差が将来の資産へ大きな影響を与えるため、運用コストが低さは非常に重要なポイントです。
運用コスト(手数料)の差が長期投資へ与える影響という内容の記事も後述しているため、よければご参照ください。
⒉ 信託報酬
インデックスファンドの保有中にかかる運用コスト(手数料)のことです。
インデックスファンドは投資家から資金を集めファンドの管理会社が運用を行うため、資産の管理や報告書作成、人件費やシステム維持費など発生します。そのため、それらの費用をカバーするために信託報酬が設定されています。
⒊ 純資産総額
インデックスファンドの純資産総額とは、ファンドに投資されている資金の合計額のことです。例えば、5人の投資家が10万円ずつ投資をしたとします。その時の合計50万円が純資産総額です。また、その資金を運用し資産が100万円まで増えたとすると、この時の純資産総額は100万円となり、このように純資産総額は毎日変動するものです。純資産総額が大きいということは、そのファンドが大きいかどうかの目安であり、資産規模が大きいほど運用の安定性が期待できます。
戦略と手法に関する用語
新NISAで運用する際に役立つ手法について実践方法を交えて解説します。
1. ドル・コスト平均法
ドル・コスト平均法とは、一定の金額を毎月同じ時期に購入することで、購入単価を平均化する手法のことで、長期的な資産形成を目指す投資方法です。また、新NISAにおいても有効な手法の一つです。
ドル・コスト平均法のメリット
・価格変動リスクを軽減できる
一度にまとまった金額を投資するのではなく、定期的に一定額を投資することで購入価格が平均化され、相場の変動リスクを抑えることができます。(価格が高いときは少なく、安いときは多く買うことができます)
・投資のタイミングを考える必要がない
今が買い時かどうかを悩む必要がなく、機械的に投資を続けられます。
・長期投資との相性がいい
NISAのつみたて投資枠のように、長期でコツコツ投資を続ける場合にリスクを分散しながら資産形成を続けることができます。
⒉ 分散投資
分散投資とは、資産を特定の投資先へ集中させず、地域や業界(セクター)、時間、資産クラスなどを異なる要素に分けて投資することでリスクを軽減する手法のことです。
・地域分散 → 例えば日本だけでなく、米国や欧州・新興国などに分散投資を行う
・業界分散(セクター)→ IT関連やヘルスケアや生活必需品など異なる業界に分散投資する
・時間分散 → 一括投資せずに、定期的に少しずつ投資する(ドル・コスト平均法)
・資産クラス分散 → 株式・債券・不動産・コモディティ(金・原油)などに分散投資する
地域や業界、資産クラスの分散投資のメリットとしては、ひとつの投資対象に依存せずに、リスクを抑えながら安定したリターンを狙うことができる点です。NISAで人気商品のS&P500(業界分散)や全世界株式(地域分散&業界分散)などのインデックスファンドは、すでに業界や地域分散がされています。
もっと詳しい内容について知りたい方は後述のS&P500とオルカン、構成銘柄や業種別の割合をご参照ください。
⒊ 長期投資
長期投資とは、短期的な売買を行わず、株式や投資信託などの資産を数年から数十年にわたって保有し、時間を味方につけて資産を成長させる投資手法です。
長期投資のメリット
・複利効果を活かせる
長期間運用することで利息が利息を生み、資産が雪だるま式に成長します。
・短期の価格変動を気にしなくて済む
インデックスファンドの価格は日々変動するものですが、過去の実績から長期では上昇しやすく、多少の暴落があっても長期的に見ると回復する可能性が高いです。
・売買の手間が少ない(ほったらかし投資)
頻繁に売買する必要がないため、時間や労力を節約できます。また、短期トレードのように買い時や売り時を常に考える必要性がありません
まとめ
新NISAは「ドルコスト平均法・分散投資・長期投資」の3本柱が基本で、焦らずにコツコツと資産を増やしていくことが成功のカギとなります。
まとめ
NISAや投資は専門用語が多く、最初はなにがなんだかわからない状態になりがちですが、専門用語をひとつひとつ理解することで、投資の仕組みやリスクなどが見えてきて、正しい判断もできるようになります。インデックス投資や分散投資などの言葉の意味を知るだけでも、どの投資方法が自分に合っているかを考えやすくなります。投資の知識が増えれば増えるほど、情報にも振り回されることなく、自信を持って資産形成を進められるようになります。この記事が、投資初心者の方の一助となれば幸いです。